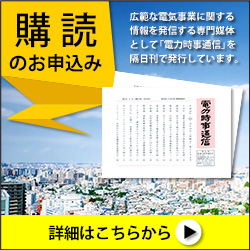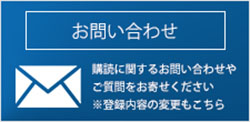東北電、中部電、九州電 次世代地熱へ期待と課題
東北、中部、九州の3電力は、このほど経産省エネ庁が初開催した次世代型地熱推進官民協議会に参加し、地熱ポテンシャルを現状の4倍以上に拡大する可能性が指摘される、次世代型地熱への期待と課題をそれぞれ示した。
次世代型地熱について第7次エネルギー基本計画は、30年代の早期実用化を目指して、研究開発・実証を進めると共に、電源構成における40年の地熱目標1~2%に向けて、地熱導入を加速するための具体的な計画や目標を策定することを提示。基本計画を踏まえてエネ庁は、環境省、林野庁、JOGMEC、NEDOをオブザーバーに、東北電グループの東北自然エネルギー、中部電、九州電グループの九電みらいエナジーをはじめとする、地熱発電事業者など計76社・団体が参加する同協議会を設置し、今年中に次世代地熱の社会実装に向けたロードマップを取りまとめる考え。
東北電グループにおける再生可能エネルギーの中核会社として、15年7月に4社が合併して設立された東北自然エネルギーは、現在リプレース中の松川地熱と、4つの地熱(計13・88㎾)を東北地域で長年にわたり運営する。そうした実績を踏まえて、次世代型地熱のうち、マグマ上部の高温・高圧流体、超臨界熱水を利用する、超臨界地熱については、開発域の拡大を期待する一方で、高い技術や想定外の事象への備えも必要―と指摘した。17年度にNEDOが実施したFS事業から、岩手県の葛根田地熱(3万㎾)でフィールド提供を行っており、仮に超臨界地熱の実証を進める場合の課題として、安全の確保、葛根田地熱への影響、地元理解の促進―の3点を挙げた。さらに、不確定な要素が多い超臨界地熱の実証では、国や関係機関の積極的な関与の下で、段階を踏んで丁寧に進める必要性を示した。
カナダのエバーテクノロジー社への出資を通じ、水を介して地下の熱を取り出す「クローズドループ地熱」の研究開発に期待する中部電は、同地熱利用技術について、将来的にエネルギー業界のゲームチェンジャーとなる可能性がある―と指摘。同技術開発で先行する、エバー社の技術概要を紹介すると共に、同社が持つ高い技術力が評価され、世界中の大手企業から資金調達している実態を説明した。
九電みらいエナジーは、967年の大岳地熱(1・45万㎾)の運開を端緒に、約60年にわたり九州内6地点(計約22万㎾)で地熱を運営する。現在も国内7地点で新規開発を推進しており、地熱開発について、従来型・次世代型を問わず、調査、運用といった地熱資源リスクを、根本的に内包していることを指摘。次世代地熱への取り組みが、地熱資源リスクの低減につながることへの期待を示した。その上で、EGS(貯留層造成)における地震誘発リスクへの対応、循環水の回収率向上といった課題や、クローズドループ、超臨界地熱での課題を挙げた。同社は23、24の2年間にわたり、NEDOの超臨界地熱技術開発への協力として、八丁原地熱(11万㎾)での実証試験(深部地熱探査手法の開発)において、既存の地熱井を試験用に提供している。