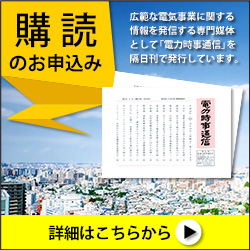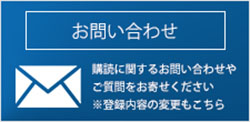関西電 博士人材採用のロールモデル事例に
関西電力再生可能エネルギー事業本部水力エンジニアリングセンターの有光剛・海外水力グループ統括課長は、企業で活躍する博士人材のロールモデルとして、このほど経産、文科両省が作成した、同人材の事例集で紹介された。
日本は海外と比較して、博士号取得者が少なく減少傾向にある。各産業の研究者に占める博士人材の割合も低く、経産省が同人材について昨年実施した調査では、同割合が米国の10・6%(19年)に対して4.2%(22年)であることも判明した。両省は、同人材の民間企業での活躍促進を図るため、昨年度に設置した検討会での議論を取りまとめ、博士を目指す学生・社会人をはじめ、大学関係者、産業界に向けて、同人材の採用・活躍に関するガイドブックと、多様な場における活躍事例を紹介する同事例集を作成した。
999年に関西電に入社した有光統括課長は、01年に技術研究所に配属され、海浜変形、耐波設計、河床変動など、海岸や河川分野の研究に従事。東日本大震災発生後は津波波力、津波砂移動などの津波関連の研究も担務した。これらの業務を行いながら、04~07年には、大学院の工学研究科土木工学専攻の博士後期課程に在籍し、業務で担当した研究課題に対して、博士論文を取りまとめ「混合砂礫海岸の漂砂移動と海浜断面形状予測に関する研究」で博士号を取得。20年から水力エンジニアリングセンター、24年には国内水力グループから海外水力グループへ異動し、海外水力事業の新規開発・保守・運用に関する技術検討を担当すると共に、京都大学特定准教授を務め、ダムや流砂環境の再生といった技術開発を進めるなど多分野で活躍している。
関西電は、大学と共同で研究プロジェクトを立ち上げることで、博士人材との接点を増やすほか、 各事業部門の専門領域において、学会やキャリア・フォーラムに参加し、博士人材との交流を深めるなど、同人材採用への取り組みを推進する。同事例集で同氏は、設計・施工・維持管理まで、土木構築物の一生を見ることができ、人々の生活を支えているところに魅力を感じ、ゼネコン、コンサルではなく電力会社の関西電に就職した経験を紹介。博士課程で身に付けた専門性・論理的思考・課題解決力・人脈は、新たな研究・業務に生かすことが可能―とした上で、学生に対して、チャンスを生かすために「迷ったらGO!」という気持ちで積極的な挑戦を期待しています―とのメッセージを送る。
なお、企業における博士人材の採用について経産省は、採用意欲はあるものの、採用できていない企業が多数あり、その約半数が、マッチングがうまくできないことを原因に挙げていることを指摘。博士人材が企業に就職する経路は、指導教員などからの紹介が多い一方で、学士修士の就活で使われる就職サイトや大学の活用が少なく、ミスマッチが生じやすい構造にあることも課題に挙げる。ガイドブックでは、各企業の採用担当者や経営者にとって、有用な採用手段や環境整備に関して、事例を交えて解説している。