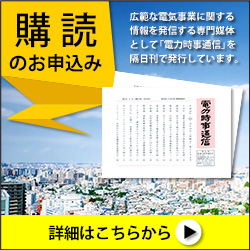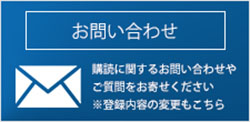国交省 港湾広域連携で風力導入加速に対応
国交省は、再生可能エネルギー海域利用法による、洋上風力事業の進展に伴って発生する課題への対応として、複数の基地港湾の関係者で構成する、協議会の設置を検討する。
洋上風力設備の設置・維持管理に利用される基地港湾には、重厚長大な資機材を扱うことが可能な耐荷重・広さを備えた埠頭をはじめ、高度な維持管理、複数の発電事業者間の利用調整が求められる。そのため同省は、国が基地港湾を指定し、特定の埠頭を構成する行政財産を、海域利用法に基づく選定事業者などに、長期間(最大30年間)・安定的に貸し付ける制度を20年に創設。これまでに青森、秋田、能代、酒田、鹿島、新潟、北九州の7港を同港湾に指定しており、昨今の基地港湾を取り巻く課題について、検討を進めているところ。このほど開催した「洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会」において、指定済み基地港湾における、着床式風力事業での利用に関する課題への対応案を提示。促進海域での案件形成の進展をはじめ、発電所の大規模化、資機材の国産化、風車の大型化など、各課題に対する検討の方向性を整理した。
洋上風力導入の目標達成に向けた案件形成が加速する中で、基地港湾の整備・利用のスケジュールが緊密化している。事業者からは、現状の基地港湾仕様では、施工期間の短縮が困難、港湾管理者からは、災害などの突発的事案が発生した際、迅速な復旧対応のための基地港湾の利用提供が困難―といった意見が挙がっている。そうした意見を踏まえて同省は、基地港湾利用の最大化を図るため、同港湾の有効利用に向けた、広域的な連携枠組みの必要性を指摘。国、港湾管理者、事業主体といった、複数の基地港湾における関係者が、一堂に会する協議会を設置し、基地港湾を一時的に利用する際の技術的課題や対応策について、広域的な連携の下で協議する仕組みを構築する考えを示した。
同協議会には、研究機関が参画し、技術的な助言を行う体制を整備。基地港湾の効率的な維持管理、最新技術の知見を活かした施設利用可否の判断など、研究機関による継続的な技術研究を進める。これらの対応に関して、同省は今後、〇基地港湾の一時的な利用に留まらない利用調整、〇利用期間の短縮、事業者の利便性向上につながる運営施策、〇各基地港湾の役割分担(分業体制)―の検討を進める。案件生成の進展に伴う利用調整に関しては、協議会の設置により、利用調整会議を拡大して広域的な連携を実現。緊急時や風車修繕においても諸手続きを経て、貸付契約を締結していない基地港湾を利用できる枠組みを想定する。