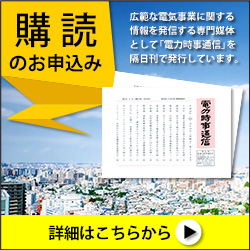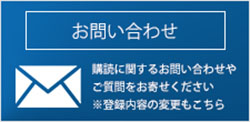ATENA リスク情報活用で意見交換を提案
原子力エネルギー協議会(ATENA)は、原子力の安全性向上に向けたリスクに関して、原子力規制庁と原子力事業者による意見交換会の具体的な実施プロセスを提案した。今年3月に開催した「主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者(CNO)との意見交換会」において、「確率論的リスク評価(PRA)に用いる機器故障率のためのデータ収集」に関する議論の中で、電力中央研究所原子力リスク研究センター(NRRC)が、リスク情報活用の全体について、規制側、事業者側が議論する場を設け、認識を共有することを求めたのを受けて、事業者側の提案を整理し、このほど開催されたCNO意見交換会で提示した。
同交換会は、原子力における「安全性の効果的な向上」の実現を目的に、具体的な活用対象(アプリケーション)を規制機関、産業界双方が複数特定すると共に、各アプリケーションの課題抽出、対応方策などを議論した上で、速やかな実施、適用を開始できる素地を整えることを想定。公開で議論を行い、資料、議事録も公開することを提案した。アプリケーションの特定では、海外実績や今までの国内検討を基に、リスク情報を活用する対象を抽出する。
ツールの整備状況、地震・津波ハザードといった情報を基に、期待できる効果を整理し、アプリケーションを複数特定する。優先順位も特定したアプリケーションに関しては、課題への対応方策を技術的、制度的・組織的な側面から検討し、各課題の検討・推進主体などを特定する。各アプリケーションの議論が完了次第、議論の結果を文書でまとめ、適用を具体的に進めるための後続の議論につなげる。これらの検討に取り組むため、1年程度にわたり同交換会を実施。規制庁、事業者、電中研NRRC、ATENAを中核メンバーに、議論に応じて、都度メンバーを追加する。