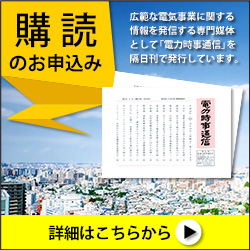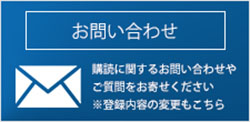警察庁 太陽光ケーブル窃盗防止へ買取規制
警察庁は、太陽光施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする「金属盗」が増加しているのを踏まえて、買い取り業者に対し、法律による規制強化を図る考えを示した。盗品の流通防止や、犯行に使用される道具に関する法規制などを含む金属盗対策について、各方面の専門家による検討を行うため「金属盗対策に関する検討会」を設置。昨年9月から議論を開始し、このほど同検討会報告書を策定した。
金属価格の高騰を背景に金属盗は、統計を取り始めた20年以降増加傾向にあり、23年には被害品のうち半数以上が金属ケーブルだった。同年の被害総額は、窃盗犯全体の被害額の約2割に相当する130億円を超えており、材質別では銅の被害が全体の約7割を占めた。太陽光施設での金属ケーブル窃盗については、外国人による犯行が6割以上に上り、同報告では、不法滞在外国人グループが犯行に及んでいる実態も指摘した。金属盗により盗まれた金属は、金属くず買い受け業者に持ち込まれるが、金属の買い受けに関しては現在、古物営業法の規制と、17道府県が制定する金属くず条例に留まり、規制対象や内容は異なっている。
同検討会は、そうした現状を確認した上で、金属くずの買い受け、金属盗に用いられる犯行用具、金属盗難に遭う恐れの大きい事業者への防犯情報の周知について、法律により実効性のある対策を、迅速に講じる必要性を示した。具体的には、まずは盗難被害の過半数を占める銅を対象として、取引時の本人確認、盗品の疑いがある場合の申告などの規制を設ける。古物に該当しない金属くずの売却については、条例を制定する道府県を除いて規制が無く、氏名などを確認することなく売却できるため、原則、顔写真付き本人確認書類の提示を求めることが望ましい―とした。
また、リサイクル業がライセンス制になっている東南アジアや中国などと比べて、国内では金属リサイクル業の許認可が無いため、適正業者の過度な負担に配慮して、届出制を導入すると共に、本人確認義務違反に対しては、何らかの制裁を行う方向で検討することを確認した。事業者などによる自主防犯対策をさらに促進すると共に、特に金属被害に遭う恐れが大きい事業者などに対しては、警察から防犯情報を周知する必要性も指摘しており、警察庁はこれらの措置について今後、立法を含めた検討を加速する考え。
太陽光施設における銅線の盗難が増加する中で、保険金の支払い総額も急増しているのを受けて、損害保険会社は現在、同盗難を原則補償の対象外としている。損害保険の引受けがない状況では、太陽光事業者が銀行から融資を受けるのは困難―といった課題解決に向けて損保は、都道府県警察とも連携して、盗難防止に向けたセミナーの開催を企画するなど、事業者への防犯情報の発信を進めている。