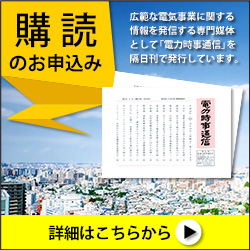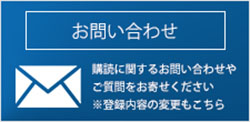エネ庁 経過措置料金の実体的役割を再検討
電力システム改革の検証を進める経産省エネ庁は、経過措置料金について、特に燃料費の急騰などに伴う電気料金の上昇局面で、料金の変動速度や変動幅を抑制し、値上げ局面においても、その上昇幅を最大限に抑制する効果があったことを指摘した。経過措置料金は、需要家保護を図るため、小売り全面自由化後の激変緩和措置として導入。経過措置期間を経た上で、料金規制の撤廃を行うことを前提に、電力10社の小売り部門に対して、家庭など小口部門の需要家が、規制料金で供給を受けられるよう義務付けた。
自由化以前の規制料金と同様に、三段階料金や燃料費調整制度などの料金体系を維持している。同庁は、その結果生じた、電気料金の上昇抑制といった効果について、必ずしも経過措置料金を措置した際に意図したのではなく、事業者の負担の下に成立したものだが、電気料金の公共性や国民生活への影響の大きさを踏まえると無視できない―と判断。同料金に関する検討課題として、同料金が実体的に果たした役割りの是非や、今後の制度的な対応の必要性、低圧需要家に対するセーフティネットの在り方・必要性などを挙げ、電力・ガス基本政策小委員会において、改めて検討する考えを示した。同料金の解除では、安定供給の確保や料金変動幅の抑制などの観点から、関連制度の検討状況などを踏まえた上で、必要に応じて適切な措置を講じる。
さらに、一般送配電事業者が担う、同料金廃止後の最終保障供給について同庁は、昨今の高圧・特高部門の最終保障供給状況を踏まえ、低圧部門で同様の状況となった場合に、一送電が平時に備えるシステムでは、実務的に対応が困難になることを想定。そのため、経過措置料金の解除に関して、一送電が小売り事業者に対し、最終保障供給の業務を委託するなどの課題も精査が必要―としている。